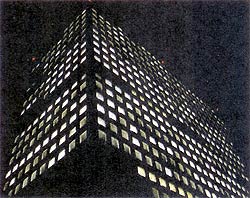シリーズ 「職場」 2006.8
|
|---|
(項目をクリックするとそこへジャンプします)
| 1. | 組合が退職強要止めた | 2. | 社長 “退職目標こなせ” |
|---|
| 3. | 「最高に腹立ってます」 | 4. | たたかって会社動かす (おわり) |
|---|
| 1. 組合が退職強要止めた
退職を強要した管理職に組合役員が 「退職強要は違法だ。 ただちにやめなさい」 と抗議しました。 会社の動きがピタリと止まりました。 この新組合員を訪ねました。 「上司に呼ばれて 『あなたの仕事を上が評価していない。 早期退職しませんか』 といわれました。 “提案” のような言い方ですが、強要の最初の一言であることはわかりました。 すぐに知り合いの組合員に相談しました」 「会社に必要な仕事をしているのに…」。 悔しい思いを語る話は、記者が質問をはさむ間もなく続きました。 外資系情報機器大手、日本IBMはいま、「リソース・プログラム」(人材計画) と呼ぶ、人減らしを実行中です。 対象となるのは、成果主義による人事評価が下位10%の 「ボトム10 (テン)」 と呼ばれる労働者です。 この計画は製造、事務などのリストラ部門だけにとどまらず、全部門に及んでいます。 そして、中高年だけでなく20代、30代の労働者も標的となっています。 同社では年1回、社員が業務目標を決めます。 会社はこれを数値化し、成果を5段階で評価します。 相対評価なので、どんなに成果をあげてもだれかに必ず低い評価がつきます。 最も評価の高い人は1(10〜20%)、次いで2、2プラス(あわせて65〜85%)、3、4(同5〜15%)。 3、4が 「ボトム10」 です。 ■ 7回迫る 「ボトム10」と評価された労働者は、会社にとって役に立たない不要な人間として退職強要の対象にされます。 断っても、「辞めます」 というまで何度でも呼び出されます。 精神的に追い詰められて、泣く泣く退職に応じる労働者が何人もいます。 1ヶ月間に7回も呼び出されて退職を迫られた体験を持つ Aさんに話を聞きました。 「今後、人事評価は上がらない」、「他部門への異動は不可能」 と決めつけられ、「ばつがついて会社の信用を失っている」 と人格を否定する言葉まで浴びせられました。 屈辱に耐えて一人でがんばりましたが、思い余って組合に加入しました。 組合が抗議すると強要はピタリと止まりました。 「会社ときちんとたたかう組合があってよかった。 この会社は、組合がないと何をするかわかりません」 と Aさんはいいます。 いま組合員は150人です。 約3分の2は、最近5年余りの間に加入しました。 (つづく) |
|---|
トップページへ <トピックスの目次の頁へ> この頁のトップへ
| 2. 社長 “退職目標こなせ”
土日もどちらか、あるいは両日とも出勤になることがたびたび。 24時間の稼働テストもあり週1回は夜勤。 退社後もトラブルで深夜に呼び戻されることもよくありました。 残業が100時間を超えた月もありましたが、請求した残業代は20〜30時間分くらい。 そのくらいが請求舜できる上限だといわれていたからです。 もとより、大半の社員は人事評価を気にして請求さえしないといいます。 ■ 「評判」 と 退職強要を受ける前年まで6〜7人のサブチームのリーダーをしていましたが、突然はずされました。 5段階評価は下から2番目。 納得がいかなかったので上司に抗議しました。 しかし、上司は理由を示さず 「あなたはなにもしていない」。 納得できず、抗議を続けると 「周りの評判」 という答えが返ってきました。 だれのどんな評判なのかは示されませんでした。 「評価なんてどうにでもつけられるわけです」 と Bさんはいいます。 ひたすら働き続けていれば報われると信じていたBさん。 リーダーをはずされた後、突然、上司に呼び出され退職を強要されました。 まったく予想外のことでした。 強要の面談は1ヶ月あまりで7回、計10時間20分に及びました。 精神的にも追い込まれ、一時は上司のいう通り再就職あっせん会社に行こうと思いましたが、全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部の機関紙 「かいな」 に相談先の電話番号が書かれていたことを思い出し、窮状を訴えました。 組合に加入し、組合が会社に抗議すると強要はなくなりました。 成果主義で競争させ、どれだけ必死に働いてもほかの人より評価が低かったら退職を強要する。 冷酷このうえないやり方です。 ■ メールで 大歳卓麻社長が管理職に送ったメールが、2002年9月ごろ JMIU支部に送られてきました。 会社のやり方に憤りを感じた管理職による告発だと思われます。 題して 「2002年リソース (編注=人材) ・プログラムの実施について」。 「会社への貢献・業績が十分でない社員ならびに将来一層の飛躍を望めない社員を対象にリソース・プログラムを展開中ですが、残念ながら6月30日のプログラム・クローズ (同=期限) を控えて十分な結果がみえていません… インセンティブ (同=力を入れること) なしにその数をこなすということは極めて困難であり… 責職自らのリーダーシップで所期の目標を達成されるよう強く要請します」 低い評価を付けた人を退職に追い込む 「目標」 を達成するために、もっとリーダーシップを発揮せよ、という社長のハッパです。 (つづく) |
|---|
トップページへ <トピックスの目次の頁へ> この頁のトップへ
同支部が行ったアンケートでは、353人の回答者のうち昇給した人が 51%、昇給しなかった人が 48%でした。 |
|---|
トップページへ <トピックスの目次の頁へ> この頁のトップへ
| 4. たたかって会社動かす
長時間勤務を常態化させているのが裁量労働制です。 2004年3月、システム・エンジニア(SE) を中心に導入しました。 全日本金属情報機器労働組合(JMIU)日本アイビーエム支部が今年2月に行ったアンケートによると、SEの残業は月平均33時間。 50時間以上が16%。 100時間以上という人もいました。 裁量制適用者には主任7万円、副主任5万円の裁量勤務手当が支給されるだけで、休日を除いてどんなに残業をしても残業手当は支給されません。 合法的な不払い残業です。 JMIU支部は団体交渉や労働基準監督署への申告を通じて、「裁量のない労働者への適用は不当」 と追及し、会社側が示した47人の裁量制適用組合員のうち43人を非適用にさせました。 労基署も動き出し、2004年12月、同社に 「裁量労働制の基準を明確にするよう」 指導票を出しました。 これを受けて社長も2005年2月、自己の裁量で勤務時間を配分できない社員への適用を中止するよう管理職にメールを出さざるをえなくなりました。 裁量労働制適用者にも昨年11月から休日出勤手当が支給されるようになりました。 日本IBMの社員は関連会社も含め連結で2万6千人。 JMIU支部の組合員は150人。 少数組合ですが、労働者の要求を掲げ、会社を動かしています。 全労働者と組合を結ぶきずなとなっているのが機関紙 「かいな」 です。 週1回 1万6千部が組合員の手で、管理職を含む社員の机上に配布されます。 組合員でない労働者から年間250万円ものカンパが寄せられ、発行を支えています。 日本IBMはいま不採算とみなした部門を労働者ごと次々に売却しています。 2003年、日立に売却されたハードディスク部門では、JMIU支部が 「社員の転籍の無効とIBM社員としての地位保全」 を求めて横浜地方裁判所に訴えを起こしています。 会社分割・労働者の転籍をめぐる裁判として全国の注目を集めています。 滋賀県野洲市にある子会社 DTI の会社清算をめぐっては 2人の組合員が解雇撤回を求めて裁判を起こしています。 ■ 組合員増 いずれもたたかいを通じて組合員が増えています。 4月にはIBM闘争支援連絡会が結成され、「リストラの毒味役IBMを告発する4・21大集会」 を 1,300人を超える参加で成功させました。 7月22日、東京都内でJMIU支部の第53回全国大会が開かれ、新組合員が紹介されました。 歓迎の拍手を送っていたBさんは3年前に加入しました。 「まずは退職強要から逃れようと入った組合ですが、組合員になって会社が何をしようとしているのかよくわかるようになりました。 納得いかないことは職場で言葉に出していうようにしています。 未払いの残業代も過去にさかのぼって請求しました」 新組合員は組合での活動や学習を通じて、みんなの権利を守る労働者に変わりつつあります。 (おわり) |
|---|
トップページへ <トピックスの目次の頁へ> この頁のトップへ