| 「労働審判」…4月スタート 〜 労働者個人の紛争に対応 〜 解雇など 迅速解決へ |
 |
|---|
「労働審判制度」 って知っていますか?
2006年4月1日からスタートする日本で初めての裁判手続きです。
働く現場では、突然の解雇や雇い止め、賃金・退職金の未払いという無法が横行しています。
こうした労働者個人と事業主による争いの迅速な解決を目的にしています。
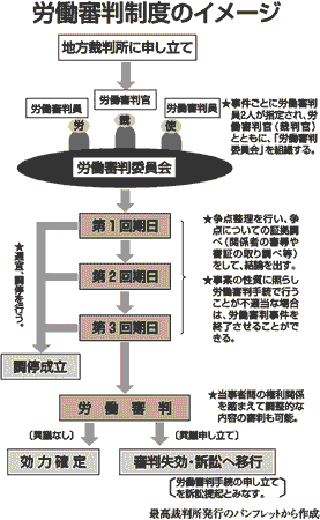 |
3回の期日で 労働審判制度は、司法制度改革のひとつとして生まれました。 全国50の地方裁判所本庁に設けられます。 申し立てをうけ、労働審判官(裁判官) と労働審判員(労働者と使用者側から任命) の計3人で労働審判委員会を構成。 争いのポイントを整理し、証拠を調べ、3回の 「期日」 (民事裁判の口頭弁論にあたる)以内に解決をはかることを原則としています。 申し立てから3ヶ月で期日を終えることを想定、短期間で争いを解決します。 その方法は、話し合いによる解決(調停) を試み、成立しない場合は審判(判決)をだします。 審判は、委員会を構成する3人の多数決によって決めます。 ◆ 審判の評決権 委員会を構成する労働審判員は、労働関係の知識をもっている人が最高裁判所から任命されます。 審判の評決権を持ち証拠調べもできます。 全国で1,000人の労働審判員がいます。 全労連、連合などが推薦した労働者側500人、使用者側推薦の500人となっています。 全労連推薦は51人。 任期は2年です。 |
|---|
◆ 強制力をもつ
労働審判は、裁判の判決と同じ効力をもちます。
相手が従わないときには、強制執行できます。
2週間以内に異議の申し立てがあった場合、審判は失効し、争いは自動的に通常の訴訟に移行します。
そのさいにも労働審判の結論がだされる可能性が高いと考えられています。
この仕組みによって労働審判の受け入れを当事者に促すと日本労働弁護団は見ています。(『労働審判実践マニュアル』)
◆ パート・派遣も
どんな争いが対象になるのでしょうか。
労働審判法第一条は、「個々の労働者と事業主の間に生じた民事に関する紛争」 と規定しています。
個々の労働者と事業主との争いを対象とし、労働組合と事業者、公務員と国・自治体との争いは除外されます。
解雇、雇い止め、賃金・退職金未払いをはじめ、労資間で通常問題になる争いを申し立てることができます。
パートやアルバイト、派遣という身分が不安定な働き方をしている労働者も当然、申し立てることができます。
労働審判は、3回の期日で解決することを目的にしており、この期日で証拠調べができない複雑な争いなどは途中で手続きが終了させられます。
トップページへ トピックスの目次の頁へ この頁のトップへ
急増する紛争
◆ 非正規雇用ふえて
大企業のリストラ、小泉内閣のすすめる規制緩和によって、パート、派遣、個人請負という働き方が急増しています。
それにともない職場は違法状態が横行し、突然の解雇、雇い止めをはじめ、個別の労働紛争が多発しています。
非正規の労働者の多くが労働組合に未加入です。
厚生労働省のまとめによると、都道府県におかれている労働局に寄せられた労働相談は82万3千件 (2004年度) に達しています。
このうち個別労働紛争は16万件を超えています。
内訳は、解雇にかんする相談がトップで27.1%、ついで労働条件の引き下げが16%となっています。
このほか全労連に、1万を超える労働相談が寄せられています。
表面にあらわれないものを含めると膨大な争いがおきていることがわかります。
労働審判制度は、多発する個別の労資紛争を迅速、公正に解決する手続きとなるよう期待されています。
◆ 金銭解決で問題も
問題点も浮上しています。
『判例タイムズ』(1194号) が企画した座談会で東京地裁の判事は、解雇が無効と判断され、労働者本人が職場復帰をのぞんでいる場合にも、金銭補償による審判をだせるとの見解を示しました。
解雇問題の金銭解決は、日本経団連などが要求し、労働者から 「金を払えば解雇してもいい … 金で解雇を買う制度だ」 と批判をあびてきました。
労働審判法第20条1項は、「当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う」 と規定しています。
日本労働弁護団は、この点を指摘し、解雇が無効と判断され、労働者が金銭解決を求めていない場合、金銭解決の審判を出すことは 「審判手続の経過を踏まえて」 おらず、「出せないものと解される」 としています。(『労働審判実践マニュアル』)
また、許可代理人(弁護士でない人)、傍聴を認めるかどうかの問題も残されています。
労働審判員に任命された人たちは、労基法などにもとづき公正、中立を貫き、労働者にとって使いやすい制度にしようと研修を重ねています。
トップページへ トピックスの目次の頁へ この頁のトップへ
最初から証拠調べ …解雇事件を“模擬審判”
労働審判制度では、審判はどのようにすすむのでしょうか。
日本労働弁護団が開いた「模擬審判」(2月25日)から流れをみます。
◇
模擬審判のケースは、家電量販店正社員の解雇事件。
33歳の男性が、解雇無効と係争中の賃金支払いを求めて東京地裁に労働審判を申し立てました。
模擬審判は、第1回期日の当日に開く事前評議のようすから始まりました。
申立書、答弁書などをもとに争点を把握します。
(1) 解雇に相当する理由があるか
(2) 申立人が労働基準監督署に違法残業の申告をした報復措置として解雇したのか
… と整理しました。
第1回期日
同委員会がただちに証拠調べに入り、会社側人事部長に質問します。
審判官: 「就業規則で午前10時始業とあるが、申立人の遅刻というのは午前9時半の朝礼に遅れることも含むのか?」
人事部長: 「はい。頻繁に遅れてきます」
審判官: 「朝礼は業務か?」
人事部長: 「店長が確認事項をのべる大事な場です」
審判官: 「朝礼に出席した場合給与の支払いは?」
人事部長: 「ありません。従業員は納得しています」
約1時間にわたって証拠調べが続きました。
第2回期日と出退勤簿、苦情処理報告書の提出、店長の同行を確認し、終了しました。
第2回期日
新たにだされた書証と店長への証拠調べを進め、一通り終わったところで同委員会は別室で評議します。
A審判員… 「解雇の理由はなく無効」
B審判員… 「勤務態度に問題があり職場復帰は難しい」
審判官… 「解雇の理由はいきさつからみると疑問。重大な理由があるとは思われない」
意見がわかれたために審判官はB審判員に再考を促しますが、見解を固持。
このため審判官は、解雇無効が2対1であることを確認し、これを前提に調停を試みます。
相手方は金銭解決を主張。
申立人は現職復帰を望み、調停は成立しません。
2週間後に第3回期日を行うことになりました。
第3回期日
事前評議で調停案をだす前提となる審判内容を「解雇は無効。解雇以降の賃金を支払え」と確認。
そのうえで、
(1) 解雇を撤回して復職する
(2) 他店への配置転換に応じ雇用を継続する
(3) 解雇から復職までの賃金を支払う
… との調停案をまとめました。
しかし、双方の主張は隔たり、同委員会は調停は難しいと判断。
審判官が口頭で審判内容(主文、理由) をのべました。
「主文、申立人が相手方(会社側) に雇用継続の権利を有することを確認する」
(出典) 日本共産党発行の 「しんぶん赤旗」 2006年3月12日(日)付、 同党のホームページ 「ここが知りたい特集」
トップページへ トピックスの目次の頁へ この頁のトップへ